コラム1
2025年12月のコラム
お子さんの足ぶらぶらはNG!
姿勢が悪いとむし歯になる!?
今月はクリスマスや年越しなど、特別な食事をする機会が多くなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな食事を楽しむためには、健康な歯が欠かせません。ところが、食事中の姿勢が悪いと歯並びにも影響し、さらにはむし歯のリスクまで高まってしまうことをご存じでしょうか?
歯並びは姿勢に左右される?
ご飯を食べるときに姿勢が歪んでいると、「片方の歯ばかりで噛む」など、悪い癖がついてしまいます。特に、足が地面に着いていないと噛む力はおよそ15%も下がる、と言われており、しっかり噛めないことであごが成長しにくくなり、歯並びが悪くなってしまう可能性も高くなります。
歯並びが悪くなるとむし歯のリスクも上がる!?
歯並びが悪くなると問題になるのは、見た目だけではありません。なんと、歯ブラシの毛先が汚れに届きにくくなるので磨き残しが増えてしまうのです。磨き残しが多いと、やがてお口の中で細菌がどんどん繁殖し、むし歯や歯周病といったトラブルを引き起こすリスクが高まってしまいます。そうならないためにも正しい姿勢で食事をすることが大切です。
足ぶらぶらに「足置き台」で対策を!
正しい姿勢で食事をするには、身体に合わせた「高さ」が重要です。まず、お子さんの背筋をピンと伸ばして椅子に座ってもらい、肘と膝の角度が直角になっているかを確認しましょう。このときに、角度が直角にならなければ、椅子の高さを調整するか、足置き台などを置いて、肘や膝が直角になるように調整しましょう。お子さんだけでなく、大人の方も姿勢が歪むと、肩こりや頭痛の原因になったり、顎関節症を引き起こしたりすることがあります。
健康な身体を作るにはよりよい生活習慣が必要不可欠です。ぜひ、ご家族みんなで姿勢をチェックしてみてください。
2025年11月のコラム
こんなことまで全部見える!
レントゲンでわかること
歯科医院でもよく使われているレントゲン。その始まりは130年前、1895年11月8日にドイツの物理学者、レントゲン博士がX線を発見した日まで遡ります。この日にちなんで、11月8日は国際的にも「レントゲンの日」とされています。このレントゲンが発見されたおかげで見た目だけではわからない疾患も見つけ出すことができるようになりました。
隠れたむし歯も見逃さない!
レントゲンでは筋肉などはX線がよく通るため黒っぽく写り、骨などの組織はX線が通りにくいため、白っぽく写ります。歯もX線が通りにくい組織であるため、健康なら白っぽく写るはずですが、むし歯になってしまった箇所は歯が溶けてX線が通りやすくなっているため、黒っぽく写るようになります。これによって、肉眼では見えないむし歯もしっかりと見つけ出すことが出来ます。
歯周病や親知らずもチェック!
レントゲンはむし歯だけではなく、歯周病の進行具合も調べる事ができます。歯周病は放っておくと歯や歯を支えるあごの骨を溶かしてしまう恐ろしい病気です。レントゲンにはあごの骨も写るため、骨の高さから歯周病の進行具合を確認することができるのです。他にも、親知らずの生えている向きを確認して、抜歯の計画を立てたり、歯の根の先に膿が溜まっていないかを確認するなど、レントゲンはさまざまな診断で活躍しています。
被ばく量は最低限なのでご安心ください!
実は、私たちは常に放射線を浴びており、年間で約2.1ミリシーベルトの被ばくをしています。他にも、たとえば日本からヨーロッパへ飛行機で一往復すると、0.1〜0.2ミリシーベルトほど被ばくすると言われています。これにたいして、歯科医院にあるレントゲンによる被ばく量は約0.01〜0.1ミリシーベルト程度であるため、日常生活における被ばく量よりも低いことが分かります。
疾患を早期発見する上でレントゲンはとても有効な検査方法です。みなさんの健康を第一に考え、レントゲンが必要かどうかは私たちが責任を持って判断していますので安心して検査を受けていただければと思います。
2025年10月のコラム
命に関わる!?
誤えん性肺炎の恐怖
栗やサンマ、サツマイモなど、秋の味覚を楽しむことができる季節になりました。旬の食材を使った美味しい料理は食卓に並ぶだけで、秋らしい雰囲気を運んでくれます。ところで、しっかりと飲み込むことが出来ないと、命に関わる病気になる可能性もあるので注意が必要です。
高齢者は特にご注意ください!
しっかり飲み込めず食べものなどの異物が気管に入りそうになると、通常は咳き込むことで異物を吐き出そうとします。しかし、高齢者の場合はそのまま気管に入ってしまう「誤えん」が起こりやすくなります。そして、誤えんが起きると、お口の中にいる細菌が気管へ侵入してしまい「誤えん性肺炎」を引き起こしてしまうのです。
誤えん性肺炎になるとどうなる?
「肺炎」はガン、心臓病、脳卒中などに次いで、日本人の死因の中で上位にいる疾患です。中でも誤えん性肺炎は、半年生存率が54.8%、1年生存率が41.8%しかない、という研究結果もあります。また、肺炎の主な症状は発熱やせき、たんなど、風邪とよく似ており、みなさんが症状から見分けるのは困難です。風邪は放っておいても良くなることがありますが、肺炎は放っておくと、入院が必要なほど重症化してしまうこともあります。特に、ご高齢の方は急激に症状が進むこともありますので、風邪症状が続くようでしたら必ず早めに内科を受診するようにしましょう。
口腔ケアで誤えん性肺炎は予防できる!
誤えん性肺炎を予防するためには、お口の中にいる細菌の数を可能な限り減らすことが効果的です。歯科医院での口腔ケアを積極的に受けた方とそうでない方を比較すると、「肺炎による死亡率を5割減らすことが出来た」という研究結果もあります。毎日の丁寧なセルフケアはもちろん欠かせませんが、それだけでは不十分です。歯科医院でプロのケアを受けることが、健康寿命を延ばす大きなポイントになります。定期的に歯科医院を受診して清潔なお口を保ちましょう!
2025年9月のコラム
気になるお口のニオイ・・・
口臭の正体とは!?
一年の中で2回旬があるのが、これから旬を迎える「椎茸」。春の椎茸は「春子」と呼ばれ、冬の寒さを乗り越えていることから旨味や栄養をたくさん蓄えていることが特徴です。一方、この時期の椎茸は「秋子」と呼ばれており、香りが強い特徴があり鍋物用として出回ることが多いそうです。ところで椎茸の香りは旬を味わうことができるものですが、世の中には非常に不快なニオイもあります。その中のひとつが「口臭」です。
厄介な口臭、その正体とは!?
人から指摘されてしまったり、寝起きにふと気になったりと何かのきっかけで、ご自身の口臭が気になってしまった経験はありませんか?口臭にはさまざまな原因がありますが、病的な口臭の約8割は「揮発性硫黄化合物」というガスによるものと言われています。
犯人は3大口臭ガス!
具体的には、「硫化水素」「メチルメルカプタン」「ジメチルサルファイド」の3つの物質が口臭の元になっています。
「硫化水素」口臭の中でも最も多くの割合を占めており、「腐った卵」に似た強い刺激臭があります。吸い込む空気によって薄められるため、口臭によって健康に害が及ぶことはほとんどありませんが、「青酸ガス」に次ぐ猛毒でもあります。
「メチルメルカプタン」腐った玉ねぎのようなニオイとも表現されますが、実は硫化水素よりも強烈です。思風病が進行すると、その毒素が原因となり口臭がさらに悪化してしまいます。
「ジメチルサルファイド」キャベツが腐った生ゴミのようなニオイとも表現されます。肝臓の病気など全身疾患が原因で発生することもある物質です。
これらのガスは、お口の中をいくら清潔に保っていたとしても、むし歯や歯周病が進行してしまうと口臭が強くなってしまうことがあります。また、これらのガスが原因の口臭以外にも生理的な口臭もあります。口臭が気になる場合は、歯科医院で相談してみてください。
2025年8月のコラム
ゴシゴシ磨きは歯の大敵!
歯を長持ちさせるには?
厳しい暑さのこの時期にはヘチマが旬を迎えます。現在では食用として栽培されていますが、かつては乾燥させたヘチマをタワシ代わりにゴシゴシと体や食器を洗うとこに使っていました。食器であればゴシゴシと磨いてもかまいませんが、実は歯みがきをするときにはゴシゴシ磨きは大敵です!歯の寿命を短くする原因になっていることがあります。
ゴシゴシ磨きは効果なし!?
歯をきれいにしようとして強い力で歯ブラシを押し付けるように磨くのは逆効果です。毛先が広がってすき間が出来てしまい、歯の表面(歯面)にキチンと歯ブラシが当たらなくなってしまうため、汚れを落とすことが出来ません。さらに広がった毛先によって歯ぐきを傷つけてしまい、歯ぐきが下がって歯の根っこ部分が露出する原因にもなります。しかも、露出した「歯の根っこ部分」はむし歯のリスクが高く、一度むし歯が出来るとどんどん進行してしまいます。
毛先の広がりで力加減がわかる!
歯みがきをするときの適切な力は150g〜200gといわれています。この力加減は、指先に歯ブラシを当てたときに毛先が開かないくらいの軽い力です。「こんな軽い力で良いの?」と思うかもしれませんが、これこそちょうどいい加減!です。毛先がキチンと歯面に当たれば、汚れはしっかり落とせます。
ポイントは持ち方!
上手な歯みがきのコツは2つ!「歯面に毛先をフィットさせること」と、「毛先を軽い力で小刻みに動かすこと」です。その際「ペングリップ」といって、鉛筆を持つように歯ブラシを持つと、力の加減がしやすいのでオススメです。当院のブラッシング指導では「お一人おひとりに合わせた磨き方」「歯ブラシの選び方」などをご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
2025年7月のコラム
「つめもの」をしたのに歯がしみる!?
痛みの原因とは
冷たい飲みものを口にしたときに、歯がしみたことはありませんか? 知覚過敏が原因と思われがちですが、むし歯の治療後にもしみることがあることをご存じでしょうか?
「つめもの」をしたのに歯がしみる!?
むし歯の治療で歯を削った場合、神経が刺激を受けたり、つめものと神経の距離が近くなるため、接着剤などの影響で痛みを感じたりすることがあります。 また、つめものを金属で製作した場合には、温度が伝わりやすくなるため、しみるように感じることもあるのです。
この痛みはなくなるの?
治療直後は神経が過敏になっているため、刺激に反応しやすい状態です。個人差はありますが、早ければ数日、長ければ1~2ヶ月程度で落ち着いていきます。 つめものをした後の痛みは、こうした一時的なものが多いので、もし痛みを感じても慌てる必要はありません。
ただし!こんなときには要注意!
むし歯が深く、神経の近くを治療していた場合に、痛みが少しずつ激しくなることがあったら注意が必要です。 他にも「かみ合わせの高さ」が原因で痛みを感じているといった可能性も考えられます。 そのため、痛みがなかなか治まらないときや1週間以上経っても違和感がある場合には、我慢せずに一度ご相談ください。
2025年6月のコラム
おいしい食事も「だ液」のおかげ?
知ってビックリだ液のパワー
6月には梅が旬を迎えます。梅の旬は短く、緑色の青梅は上旬、黄色の完熟梅は中旬に出回るそうです。梅の代表的な加工品といえば梅干しですが、見ているだけでも思わずだ液が出てしまいますよね。そんなだ液ですが、実はいくつもの重要な役割があることをご存じでしょうか。
おいしく感じるのはだ液のおかげ!?
「ひと口噛む毎に、口の中に味が広がる」このような繊細な変化を楽しめるのは、実はだ液のおかげ。だ液が食べ物と混ざり合うことによって、舌が味を感じやすくなるのです。さらに、食べものを上手に飲み込めるのも、だ液に「お口を潤す」という力があるおかげです。もしもだ液がなかったら、何を食べてもパサパサして味の無いクラッカーをたべているような感覚になってしまうことでしょう。
むし歯から歯を守っている!?
だ液には「歯を虫歯菌から守る力」もあります。歯の表面についた汚れを洗い流し、さらには、虫歯菌によって溶かされた歯を修復する、という重要な働きもあります。もしもだ液が無かったら、あっという間にむし歯になってしまいます。また、だ液には「抗菌作用」が含まれており、インフルエンザなどの予防にも効果があることがわかっています。
だ液ってこんなに出るの?
なんと、だ液は1日に1~1.5 L もの量が分泌されます!しかし、この量は加齢や生活習慣などによって減少し、豊かな食生活が失われ、むし歯や歯周病・感染症のリスクが高まってしまいます。そこでオススメしたいのが「パタカラ体操」です。「パパパパ・・・」というように「パ」「タ」「カ」「ラ」をそれぞれ素早く10回ずつ、これを3周繰り返しましょう。継続して行えば、お口の周りに筋肉がつき、だ液がしっかり分泌されるようになります。また、「あいうべ体操」もオススメですね。口を大きく「あ~い~う~べ~」と動かします。「べ~」は舌もいっぱい出してください。とても簡単な体操なので、ぜひ空いた時間にチャレンジしてみてください。
2025年5月のコラム
ご存じですか?
メタボリックドミノとは
私たちの健康も、気づかないうちにひとつの乱れから連鎖して、ドミノ倒しのように大きな不調へとつながることがあります。今回はそんな「メタボリックドミノ」について御紹介します。
メタボリックドミノとは!?
肥満に加えて高血圧や高血糖、脂質異常症(高脂血症)となった状態を「メタボリックシンドローム(通称・メタボ)」といいますが、これらすべてがお口とも深く関わっています。メタボを放っておくと脳血管疾患・心血管疾患などの「命に関わる病気のリスク」が高まります。そのメタボの原因として、恐らくほとんどの方が一番に思い浮かべるのが「肥満」でしょう。では、その「肥満の原因」はなんだと思いますか? このように、「肥満になるからメタボになる、メタボになると動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが上がる」といった負の連鎖を「ドミノ倒し」にたとえたものが「メタボリックドミノ」です。
秘訣は「上流で食い止める」こと!
つまり、「最初のドミノ」を倒さなければ、その先の病気を防げるということなのですが、一番上流にある病気こそが「むし歯」と「歯周病」なのです。むし歯や歯周病を放置しておくと、細菌が身体の隅々にまで害を及ぼし、脳梗塞や糖尿病、誤えん性肺炎や心臓病などを引き起こす恐れがあります。
全身の健康はお口から!
お口の健康は、身体の健康と密接なつながりがあります。歯がしっかりそろっていれば、食べられるものが増え、たくさんの栄養素を取り入れることができる上、よく噛むことは肥満防止にもなります。お口のケアをしっかりと続け、最初のドミノを倒さないようにすることが、さまざまな病気の予防にもなります。みなさまの健康を守るお手伝いを、ぜひ私たちにもさせて下さい。
2025年4月のコラム
百害あって一利なし!
タバコで歯が無くなる!?
タバコは全身だけでなく、お口の健康にも悪影響があります。つまり、大切な歯を守るためには、タバコとの付き合い方を見直すことが大切なのです。
歯周病になりやすくなる!?
タバコを吸う人はそうでない人と比べて歯周病にかかりやすく、さらに重症化しやすいといわれています。ニコチンなどの有害物質が血管を収縮させ、血流を減少させます。すると、体は酸欠、栄養不足の状態となり、病気に対する抵抗力などが弱っていくのです。もちろん、それは歯ぐきにも同じことが言えます。その上、有害物質の一部はヤニ汚れとして歯にこびりつきます。ヤニは見た目を悪くするだけではなく、表面がざらざらしているため、歯周病の原因となる歯垢がつきやすくなり、歯周病を悪化させます。
タバコで歯を失う!?
歯周病は「沈黙の病」と呼ばれるほど、自覚症状が少なく、静かに進行する病気です。そんな歯周病の数少ないサインが「歯ぐきからの出血」なのですが、タバコによって血流が減少していると、このサインに気づきにくくなります。また、タバコの煙には200種類以上の有害物質が含まれており、傷ついた歯ぐきや骨を治そうとする働きを弱めてしまいます。そのため、気づいたときには歯周病がかなり進行していて、歯を支える骨が溶け、歯を失う結果になることも珍しくありません。
歯周病予防は禁煙から
近年では煙やニオイの少ない加熱式のタバコを愛用する方も増えていますが、決して無害というわけではありません。禁煙も歯周病予防も始めるのに遅すぎる、ということはありません。「今更手遅れだから・・・」と諦めずに、ぜひチャレンジしてみてください。
2025年3月のコラム
自覚がなくても要注意 !?
骨粗しょう症と歯周病に深い関係が!
骨がもろくなって骨折しやすくなる「骨粗しょう症」とお口の病気である「歯周病」。無関係と思われがちですが、実は深い関係があります。
骨粗しょう症患者の8割は自覚なし!
骨粗しょう症になると、軽く転んだだけでも脚の骨や背骨などを骨折してしまい、寝たきりになってしまう方も少なくありません。日本に推定患者数は1000万人以上おり、約8割は自覚がないと言われています。
重度の歯周病率は90%以上とも!
骨粗しょう症を発症する原因は、加齢、運動不足、生活習慣などさまざまですが、そのひとつに「エストロゲン」というホルモンの減少があります。このエストロゲンの減少は骨粗しょう症だけでなく、歯と歯ぐきの間などで炎症を引き起こしやすくなり、歯周病が悪化してしまうことも。実は骨粗しょう症を患う人の90%以上が「重度の歯周病にかかる」と報告されています。さらに、骨粗しょう症によって歯を支える骨も弱くなることから、より歯が抜けやすい状態になります。
骨粗しょう症の薬は歯の治療に影響します
また、骨粗しょう症とお口には、お薬でも深い関係があります。骨粗しょう症の患者さんによく使われる「BP製剤」というお薬は、骨が生まれ変わるスピードを遅くする働きがあります。たとえば、抜歯などの処置をきっかけに細菌に感染し、あごの骨が炎症を起こすことがありますが、この時にBP製剤を飲んでいると、骨の生まれ変わるスピードが遅くなっているため、傷が治りにくくなります。最悪の場合、あごの骨が壊死(えし)してしまうこともあります。病気の治療などでお薬を飲んでいる方は、治療前に必ずご相談頂きますようお願いいたします。
骨粗しょう症も歯周病も自覚症状の少ない病気です。もし、骨粗しょう症と診断されたら、必ず歯科医院で歯周病のチェックを定期的に受けるようにしましょう。
2025年2月のコラム
歯ブラシ交換は
定期的にしよう!
まだまだ寒い日々が続いていますが、「寒い時期にはトイレが近くなる」と言われています。冷たいものや水分を摂りすぎないこと、軽めの運動で適度に汗をかくことが対策になるそうです。さてトイレといえば、みなさんの身近なあの道具に、実はトイレの水よりも多くの細菌が潜んでいることをご存じでしょうか。
トイレの水よりも汚い!?
みなさんが歯ブラシを最後に交換したのはいつ頃でしょうか? 長い間使い続けた歯ブラシには、見た目で分からなくても大量の細菌が潜んでいます。 ある研究によると、「3週間も使用すれば、最近の数は100万個以上になる」とも言われています。 実はこの細菌数は、トイレの水に潜んでいる細菌数のおよそ80倍にもなります。 たとえ完璧に歯みがきをしたとしても、使う道具が汚れていては細菌をこすりつけているようなもの。 最低でも3週間~1ヶ月に1回は歯ブラシを交換するように心がけましょう。
見た目でも分かる!交換の目安
歯ブラシを後ろから眺めてみてください。 このとき、毛先が広がって歯ブラシのヘッドと呼ばれる頭の部分が、柄の部分からはみ出していたら使用期間が短くてもすぐに新しいものへ交換しましょう。 このような歯ブラシは、毛先の弾力が失われているため汚れを落としづらくなっています。 さらに、広がった毛先で歯ぐきを傷つけてしまう可能性もあるので注意が必要です。
歯ブラシを衛生的に使うためには?
長く衛生的な状態で歯ブラシを使用するには、使ったあとの管理が大切です。 使い終わったら流水で洗いよく乾燥させましょう。 また、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシなどのケアグッズについてもご相談を承っています。 気になることがありましたら、お気軽にお声お掛けください。
2025年1月のコラム
忍び寄る恐怖!
歯みがきで落ちないバイオフィルムとは?
さて、皆さんは「バイオフィルム」をご存じでしょうか? 「バイオフィルム」とは細菌が集まり、膜状になったものです。キッチンの三角コーナーや排水口についてしまう「ヌルヌル」もそのひとつです。 なんと、あの「ヌルヌル」は、お口の中にも発生します。
お口の中にも排水口のヌルヌルが!
お口にできる「バイオフィルム」の正体は、皆さんもご存じの「歯垢」です。実は、歯垢とは単なる食べかすではなく、細菌の塊のことです。なんと、1mg あたり1億個もの細菌が存在しています。この歯垢を放っておくと、細菌が強力な膜を作り出しヌルヌルしたバイオフィルムになってしまうのです!
バイオフィルムを放置するとどうなるの?
細菌をすべて取り除くことは出来ないため、残念ながらバイオフィルムは必ず出来てしまいます。しかも、通常なら細菌は「だ液の力」によって殺菌されますが、バイオフィルムは強力な膜に守られているため、だ液も効果を発揮できません。さらに、バイオフィルムは歯みがきでしか取り除くことが難しく、取り切れないまま放置するとその内側で細菌がどんどん増殖してしまいます! すると、むし歯や歯周病のリスクが高まってしまうのです。
バイオフィルムを撃退するには?
バイオフィルムを取り除く方法は、歯科医院でプロによるケアを受けることです。歯科医院では歯石の除去だけでなく、こうしたバイオフィルムもしっかりと取り除くことが出来ます。 一方でどちらもご自身ではなかなか取り除くことが出来ません。 そのため、必ず定期的にお越しいただきお口の中を清潔な状態に保ち、健康な毎日をお過ごしください。
2024年12月のコラム
縁の下の力持ち!
歯根膜って何者!?
年末には「年越しそば」を食べる、という方も多いのではないでしょうか。地域や家庭によって異なりますが、天ぷらやかき揚げ、きのこ、鴨肉など様々な具材から好みのものを入れるのも楽しみのひとつですね。
こういった食事を楽しむために欠かせないのが「歯ごたえ」ですが、お口の中のどこで感じとっているのかご存じでしょうか?
歯ごたえを感じとっているのは・・・
「歯」や「歯ぐき」・・・ではありません。実は、私たちが「歯ごたえ」を感じとっているのは、「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれる薄い膜によるものなのです。歯は「歯槽骨(しそうこつ)」と呼ばれる骨に支えられているのですが、この骨と歯の根っこの間にある薄い膜が「歯根膜」です。歯根膜はとても薄く、その厚さはたったの 0.3 mm 程度しかありません。
歯を守る重要な役割も!
歯根膜の役割は、歯ごたえを感じ取るだけではありません。歯根膜はクッションの役割も果たしています。皆さんは何気なく毎日の食事をしていると思いますが、この時にとても強い力が歯や骨にかかっています。しかし、歯根膜がこの強い力を吸収・分散してくれることで歯や骨を衝撃から守ってくれているのです。
歯根膜を守るために・・・
このように重要な役割を担っている歯根膜ですが、実は歯が抜けると、歯と一緒に取れてしまいます。つまり歯を失って、入れ歯やブリッジになってしまうと、見た目や咬みやすさの変化だけでなく、食感を感じることも出来なくなってしまうのです。いつまでも美味しく食事をするためには、天然の歯を1本でも多く残すことが不可欠です。磨き残しのないように、日頃の歯みがきの徹底や歯科医院での定期的なメンテナンスでしっかりと歯を残して、おいしい食事を楽しみましょう!
11月のコラム
予防しよう!
むし歯リスク3大ポイント
11月8日は「いい歯の日」です。「いつまでもおいしく、楽しく食事をとるために、お口の中の健康を保っていただきたい」という願いを込めて制定されました。
健康なお口を保つためのポイントはいくつかありますが、その中でも特にケアするべきむし歯リスク3大ポイントを御紹介いたします。
奥歯の「みぞ」にご用心!
1つ目のポイントは、奥歯の「みぞ」です。「みぞ」は見た目よりもとても複雑な形をしています。そのため、歯みがきをする際にうっかり力を入れすぎてしまうと毛先が曲がってしまい、磨き残しが生まれてしまいます。
・垂直にあてる ・力を入れすぎない ・小刻みにかき出す
歯を磨く際には、この3つを意識することが大切です。奥歯は全体を一気に磨くのではなく、1本ずつ丁寧に磨いていくのがポイントです。
歯ブラシだけでは取り切れない!?
2つめのポイントは、歯みがきに使う道具です。歯ブラシだけでは汚れ全体のうち、6割程度しか取れないと言われています。特に歯と歯の間は、歯ブラシに毛先が入りにくいため、汚れが残りやすく、むし歯や歯周病になるリスクがとても大きいのです。そこで活躍するのが、歯間ブラシやデンタルフロスです。汚れの除去率がグッと上がります。ただし、お口の状態によって、適切な用具やサイズが変わりますので、ご不安な方はぜひ一度ご相談ください。
歯ぐきが下がるとこんなところにも・・・
3つめのポイントは、歯の根っこの部分です。歯の表面は「エナメル質」という人体の中で最も硬いと言われている組織で守られています。しかし、歯ぐきが下がって、露出した根っこの部分にはエナメル質がありませんので、むし歯になりやすいのです。根っこが露出してしまっている場合には、フッ素入りの歯みがき粉で優しく磨くのがオススメです。また、露出の原因のひとつは、歯周病による歯ぐきの下がりです。つまり、歯周病予防をしっかりとしておくことが、むし歯予防にもなると言えます。
歯周病は自覚巣状が少なく、歯の根のむし歯は進行がとても早いので、見落としてしまうことがないように歯科医院で定期的にチェックしましょう!
10月のコラム
「痛みがなくなってラッキー」は
大間違い!大切な歯の神経
10月15日は「世界手洗いの日」です。正しい手洗いを広めるため、2008年にユニセフが定めました。石けんで手を洗うことの大切さや、正しい手洗いの方法を正しく伝える活動が行われています。
大切といえば、歯の神経もご自身の歯を使い続けていただくために、とても大切な役割を担っています。
歯の神経の役割とは!?
歯の神経には「痛み」や「しみる」といった感覚を伝える役割があります。「痛みを感じるくらいなら、神経なんてない方がいい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。「痛み」や「しみる」といった感覚があるからこそ、むし歯に早く気がつくことができます。
他にもこんな役割が!
神経には歯に栄養を運ぶための血管も通っています。しかし、神経をとる治療をすると、この血管も失われてしまいますので、歯に栄養が行き届かなくなります。すると、神経をとった歯は枯れた木のように、もろく、欠けやすくなることもあります。丈夫な歯を保つためには、神経を守っていくことも大切なのです。
神経をとらないといけないことも・・・
むし歯ができてしまっても、大切な神経を残すことができるよう歯科医院では最善を尽くしています。しかし、むし歯が大きくなり、神経を傷めている場合などには、やむを得ず神経をとらなければなりません。神経をとると痛みを感じにくくなりますが、その後むし歯にならなくなるわけではありません。むしろ、神経をとった歯は、むし歯になっても気がつきにくいので、発見が遅れてしまいがちです。早期に発見するためには、歯科医院でのチェックが必要不可欠です。
ぜひ、定期的にご来院いただき、皆様の大切な歯と神経を守っていきましょう!
9月のコラム
大人の歯と子どもの歯は
何が違うの?
9月24日は「歯科技工士記念日」です。1955年9月24日に「日本歯科技工士会」が誕生したのを記念し、制定されました。歯科技工士は、入れ歯やつめもの、かぶせもの、矯正装置などを製作する国家資格を持った専門職です。みなさんの見えないところで歯科医療を支えている縁の下の力持ち的な存在です。
ところで大人の歯である「永久歯」と子どもの歯である「乳歯」は何が違うかご存じでしょうか?
乳歯の厚みは永久歯の半分?
乳歯と永久歯の違いは、歯の「質」と「厚み」。乳歯は永久歯よりも柔らかいため、比較的むし歯になりやすいといえます。さらに、歯の表面を覆っているエナメル質やその内側にある象牙質と呼ばれる層が、乳歯は永久歯の半分程度の厚みしかありません。そのため、むし歯になってしまうとすぐに神経に達してしまうので注意が必要です。
どうやって永久歯は生えてくるの?
歯は「歯胚(しはい)」というタネのようなものから形成されていきます。なんと、永久歯の歯胚が作られるのは生まれる前の胎生3ヶ月半頃のことです。やがて歯胚が成長し、根までできた頃に「そろそろ生えるぞ」という信号を乳歯に出します。すると、乳歯の根が溶けだして、永久歯へと生え替わるのです。
乳歯のころから歯を大切に!
もしも、永久歯を失ってしまうと皆さんの健康にも大きな影響が及びます。しかし、乳歯の頃から歯を大切にしておくと生えてくる永久歯も丈夫になり、大人になっても歯をケアする習慣が身につきます。乳歯も永久歯も大切な歯であることに変わりはありませんので、お子様のためにも幼い頃からセルフケアを徹底していきましょう。
8月のコラム
抜歯後に気をつけること!
ドライソケットとは!?
抜歯をした跡が気になって、触ったり掻いたりすると、強い痛みを引き起こすことがあります。もし抜歯後に強い痛みが続いている場合、それは「ドライソケット」かもしれません。
抜歯後に強い痛みが・・・
歯を抜くと、歯ぐきにぽっかりと穴が空き、骨がむき出しになります。通常はその穴に血液がたまって「血餅(けっぺい)」となり、時間をかけて治っていきます。しかし、血餅がうまく出来なかったり、血餅が剥がれてしまったりすると、顎の骨がむき出しになってしまいます。その骨が細菌感染を起こした状態を「ドライソケット」といい、強い痛みの原因となります。
ドライソケットを防ぐには・・・
抜歯後は約1~2日後までに空いた穴に血が固まり、血餅が出来ます。ところが、抜歯後に何度も強くすすぐような激しいうがいや、傷口を舌や指などで触れるなどの行為はせっかくできた血餅を剥がしてしまう恐れがあります。気になっても触らないようにした上で、血餅が定着するまでの数日間は歯ブラシが直接触れてしまうことがないように、優しく歯磨きをするなどご注意ください。また、タバコを吸う方は特に注意が必要です!喫煙は血流を悪化させてしまうため、ドライソケットの原因になりやすいと言われています。
もしかしてドライソケット?
通常の場合、抜歯をすると数日は痛みが出ることはあります。しかし、ドライソケットになると強い痛みが10日~2週間程度も続くこともあり、痛みが落ち着くまで1ヶ月ほどかかることも。「痛みがずっと続いている」「数日たったら痛みが強くなってきた」などの違和感を覚えたら、どうぞ歯科医院にご相談ください。
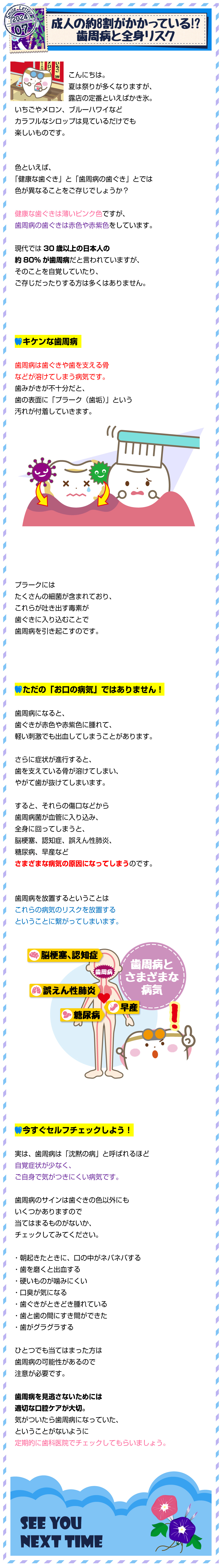
7月のコラム
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ▲ | ─ |
午前:09:00~13:00
午後:14:30~18:30
▲:14:30~17:30
※祝日がある週の木曜は診療します
休診日:木曜・日曜・祝日

